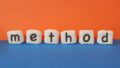家族信託って?
家族信託とは、金銭や不動産などの財産をを信頼できる家族などに託して管理・活用してもらう制度です。
家族信託は、財産を持っている人(委託者)と財産を管理する人(受託者)が信託契約を結びます。
受託者が財産を管理した結果、利益を得る人を受益者と言います。
受益者と委託者が同じ人になることもあります。
例えば、委託者本人が認知症になった場合に受託者が託された財産を使って委託者の面倒をみる様な場合です。
どんな時に家族信託を活用するのが良いのか
認知症対策
祖父母や両親が認知症になった場合、銀行口座が凍結されることがあります。
事前に一定の金銭を受託者に託すことで、銀行口座凍結後もその金銭を生活費や医療費にあてることができます。
また、祖父母や両親が賃貸マンションなどの不動産経営をしている場合、賃貸用物件を受託者に託すことで認知症になった後も事業が継続され、収益を利用することが可能になります。
親亡き後問題対策(知的障害がある子供を守るための信託)
知的障害がある子供に財産を残しても、うまく財産が使えるのか、騙し取られないか、といった心配が残ります。
そこで信頼できる兄弟姉妹などに財産を託しておいて、その子のために財産を使ってもらうようにします。
家族信託のメリット
- 信頼できる人に財産管理を任せることができる
- 信託財産の売却など、任意後見制度と比べて柔軟な財産管理を行える
- 信託財産の名義を形式上受託者に変更することで、委託者が認知症になっても銀行口座の凍結などの影響を受けない
- 不動産を受託者の単独名義にすることで、共有名義にした場合の問題(共有者全員の同意が得られず売却や大規模修繕ができない)を回避できる
- 委託者が亡くなった後の信託財産の行方を決めることができる(遺言代用型信託)
- 二次、三次受益者を設定しておくことで、受益者より後の財産の行方を決めることができる(受益者連続型信託)
- 委託者が経営者の場合、経営権を託すことで事業承継を円滑に行うことができる
家族信託のデメリット
- 信託の内容によって、受託者の負担が大きくなる
- 信託財産から一定の収益がある場合、受託者は税務処理の負担が発生する
- 家族信託そのものに相続税対策の効果がない
- 相続人による財産の処分を長期間制限すると、かえって相続人間の紛争を招く可能性がある
まとめ
家族信託にもメリット・デメリットがありますので、個々のケースで任意後見制度を利用するのか、遺言や生前贈与を利用するのか、慎重に検討する必要があると思います。
活用を検討する際には、専門家と相談することをお勧めします。
なお、家族信託の契約書は公正証書で作成します。
行政書士でも原案を作成できますので、是非ご相談ください。
信託財産に不動産がある場合は、信託登記をする必要があり行政書士では行えませんが、司法書士さんと連携して対応しますのでご心配不要です。